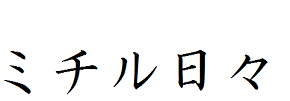梨木果歩さんの新作『海うそ』は、もうずいぶん前に読了した。
なのに、咀嚼しきれない何かがあって、また再読。
私にしては珍しく、書店に並ぶなり買って(4月中旬!)、寝かせもせずにすぐ読んで、なのにレビューはやっと今ごろになりました。
梨木さんは、『西の魔女が死んだ 』(新潮文庫)や『からくりからくさ』 (新潮文庫) などを発表した初期のころから、独特の世界観で読者をひきつけ、物語の底流にはいつも大いなるモノ(=カミサマとか、不思議な世界とか)を置いていたように思います。
だけど、読者が物語の深みにはまるほどの深淵さを前面には押し出さなくて、たぶん多くのヒトは、楽しく読んで、ココロを少し豊かにして本を閉じたはず。
それが、ここ最近の作品といったら、どんどん深いほうへ深いほうへと向かっているかのようで、読者は、いっしょに深みにずぶずぶと嵌らざるおえない。
そして、その深みからいったん這い出し、こんな個人ブログとはいえ、他の誰かに向かってレビューするなどもってのほか。
そこまでしっかり理解をしているだろうか…私。
…などと思ってしまうのである。
だけど、難しいけどやっぱりここにレビューしとかなきゃ、だって好きな作家だもの。
…と逡巡までする。
ああ、罪な作品でもあります。
美しい装幀にこのちょっと暢気そうなタイトルが曲者なんである。
『海うそ』という本は、美しさのなかに少し暢気なエッセンスをまぶしたようなルックスで書店に並び、手に取って開いてみれば、そこには、(たぶん)架空の島・南九州の遅島の地図。
あれれ?冒険小説とかかな?
とも思わせ、とにかくいっけん、楽しげなんである。
実際、最初は、人文地理学者である主人公・秋野が巡る島を、冒頭に添えられた地図を片手に一緒に巡るように読む。
ただひたすらにその読み方が、楽しかった。
テーマは、大いなるものへの「畏怖」を忘れてゆく歴史…といったらいいか
途中、その島が、廃仏毀釈の最前線のような扱いを受けたのだと知るにつれ、徐々に旅の意味が重みを増してくる。
そこで、読者は「ああ、まただ」と思い、ちょっと姿勢を正してみたりするのである。
かつて、修験道の霊山があった島。
それとは別に島の民間信仰として、海で死んだ霊魂を慰める宗教的存在であったモノミミという存在がいた。
さらに、ずーっと過去には、平家の落人伝説や、江戸時代の悲恋物語まで、遅島は、日本が失ってきたモノの記憶の集積を内懐に抱えていた。
かつて、神仏分離令が発布された明治時代。
それを契機に国学者や神職が起こした過激すぎる仏教廃絶運動は、遅島にある、修験道の霊山を破壊する。
仏寺・仏塔・仏像などが一網打尽にされたのはもちろん、多くの僧侶が還俗を強要された。
「廃仏毀釈」の名のもとに行われた暴力は、素朴な民間信仰までも壊滅させようとして、モノノミがいた痕跡も消し去ってゆく。
これは、おそらく当時、日本全国で巻き起こったであろう喪失の歴史でもあって、それを追体験するかのように島の傷跡を巡る旅は、苦痛である。
そして、戦争。
またも、国策無策によって多くのモノが失われてゆく歴史が続く。
そしてエピローグでも続く喪失。
<それから戦争を跨いで五十年が経った。>で始まるその最終章は、暢気にその後の平和な日本を語るものではなく、そこにも作家の見識の深さを感じるのである。
秋野は、戦後も生き、そして縁あってまた、50年前の遅島へ。
島は、再開発という名のもとに、またも大切なモノが破壊されようとしていた。
霊山は、削られ。
由来ある岸や絶壁も護岸され整えられる。
素朴な島は、人工的なリゾート地へと…。
もしかすれば、これは、廃仏毀釈や戦争よりも、暴力的喪失?
明るく清潔、豊かそうな仮面をかぶっているから、もっとも始末に負えないのかも。
富国強兵のための国策や経済発展とかを大義名分に掲げ、時代の流れとともに少しずつ失ってきた、豊かで大切なモノ。
それは、物質的なモノはもちろんなのだけど、それを超えて、大いなるモノを畏怖するココロみたいなもの。
50年前の遅島を、秋野と巡った読者はそれをどう考えてよいのかわからず途方に暮れる。
…うーん。
やっぱり、梨木果歩の作品は、もはや、気軽には読み解けない感じ。
でも、ぜったい無視できないのは、始終一貫して、自然の中にある、大きな存在をテーマに据え続けているからだと。
ヒトは、それを忘れては生きていけないからだと。
読者はみな、それを知っているからなのである。