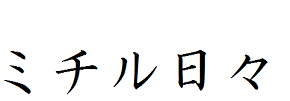『ふたりからひとり ときをためる暮らし それから』を惜しみつつ読了。
ントに読み終わるのが惜しかった…と思える一冊。
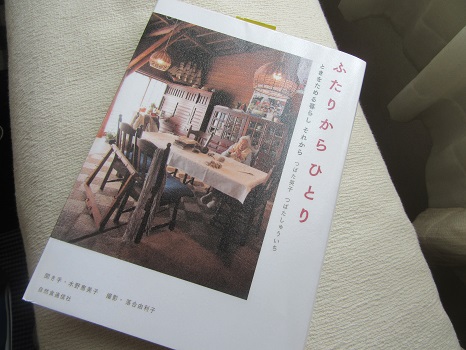
私は、このシリーズの最初から、つばた夫妻の穏やかで豊かな暮らしに憧れつつ、次の一冊が出ないかなぁと静かに楽しみに読んできた読者。
だから、書店で一応…とこの夫妻の著作がありそうな場所を探したある日。
夫であるつばたしゅういちさんが逝ってしまったことを知る。
知って、少し唖然となって、がっかりもし、しかし、本屋さんで静かに訃報に触れるのも、なんからしいな…と。
本書は、つばたしゅういちさんが逝った日以降に編まれた一冊。
もういないひとを思って、そして、残された英子さんを思ってページをめくり…冒頭。
プロローグに書かれた、しゅういちさんによる「人生が完成する日」を読んで、そこにその人の強い存在感。
生きる意志、生きた証…みたいなものを感じてまずホッとした。
そして、次に、夫妻の住まいと庭(畑と雑木林)の写真が続き、その美しさにため息をつく。
逝ったと思ったけれど、その庭に、その家に、つばたしゅういちさんは宿っているんだなぁ…とふと。
いや、読み進むにつれ、英子さんも、夫妻の娘さんも、そんな風に言っていて、これは確信となってゆく。
描かれた物語は…。
しゅういちさんが、逝った日から始まって、あとは、時間を少し巻き戻して、体調を崩した夫を、食養生で支える妻のお話。
…とも読めるけど、そこにはなんの切迫感も焦りもなくて、それも静かで豊かだ。
我が人生の先輩は、やっぱりさすがだなぁ…などと勝手に思って、最後のページをそっと閉じた。
今、同じような読書体験のできる一冊を探そうと思っても、なかなかなくて、だから、本書も後生大事に書棚にしまう。
英子さんはひとりになってしまったけれど、その後の、暮らしもまた一冊にしてほしいなぁとも思いつつ、今は、あるだけの数冊を、時々、取り出しては眺め、よりよく生きたヒトたちの証に、読者はため息をつくのである。
いやはや、なんともステキすぎる一冊なんである。
…特に「時をためる」という生き方が。