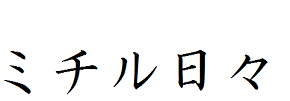幸田真音氏の作品は、いつも「ヘッジファンド」とか「国債」とか「企業買収」など、硬派経済ネタをテーマにしつつも、そこに凛とした女性を主人公に据えて、エンディングはいつの爽快な物語。
幸田真音氏の作品は、いつも「ヘッジファンド」とか「国債」とか「企業買収」など、硬派経済ネタをテーマにしつつも、そこに凛とした女性を主人公に据えて、エンディングはいつの爽快な物語。
…というのが、いつも気になってしまう理由。
でも、今作は、ちょっとおもむきが違う。
そもそも、珍しすぎるコトに、主人公は、ダンディな男性。
物語は、実在の人物・「サンモトヤマ」創業者・茂登山長市郎をモデルとした昭和の商人の半生を描く一代記だ。
エルメス、グッチをはじめ数々の西洋の一流品は、いったいどうやって日本に紹介されて今にいたったのか。
その物語は、戦時下、主人公が派兵された中国大陸・天津でのエピソードから始まって、戦後、東京の焼け野原の闇市での様子と続く。
そして、そこで小さな成功を修めて渡欧。
当時、敗戦国のしかも名も知れない貧乏な極東の国の人間が、海外メゾンの高級品の日本販売権を獲得するための高すぎる壁を、直感と「モノではなく美しい文化を日本に売りたい」という、熱意だけで乗り切ってゆく。
そして、1970年代、当時、まだ誰も知らなかったグッチを、ついでエルメスを日本人へも紹介するにいたった。
その造り手である職人を育てるところから手間隙かけて大事につくったモノ…ということを深く理解した人間が、それを大事に売るという…この時代こそが、日本にとってのラグジュアリーブランド真の黄金期だったのだということが描かれていて、清々しさを感じる。
が、それもつかの間。
そこにも、資本力と株価・配当収益優先の原理資本主義の波が押し寄せて来て、90年代には、50億にも成長をとげた日本販売権の返還をせまられる。
かくして、今。
海外メゾンの外資資本による日本の現地法人化の波は、銀座やデパートのいちばんいい場所をブランドショップで独占させてその場の個性を変えた。
まだそれは良しとしたとして、とうとう高級品の「アウトレット」という売り方まで登場し、ありえない「高級品」と「大量販売」の組み合わせ。
職人の高い技術と高級素材からなる美しいクラフト。
その累々と積み重なった歴史からくるしなやかだが強い矜持。
そんな背景を持つモノに喜びを感じ長く大切にするという「人の思い」よりも「大きな利益」…という図式がここにもあったのか…といまさらながら。
…と、エルメスにもグッチにも縁がない私でさえもついついマジモードで読み進むハメになる。
いつも読者にこれからのヒントと勇気をくれる幸田風は健在
これは、敗戦から昭和の高度経済成長、そしてバブル崩壊、原理資本主義の波、そしてリーマンショック以後までを美しいモノを通して俯瞰した物語であるが、いつも痛快エンディングでもって読者を勇気付けてくれる幸田風はかわらない。
物語終盤、茂登山長市郎氏をモデルとした主人公は87歳であるものの、「美しいモノ」を探す旅はまだ終わらず。
今度は「美しく稀少な素材」と「その造り手」探して、アジアや南米の高地、北極近くまで冒険の旅。
彼は、「百年に一度の不況といわれている今のほうが、本当は面白いのかもしれないよ。こうゆう混乱期はチャンスがごろごろしているから」と言ってのけ、だから「こうゆう大きな節目のときは自分も堂々と変われるんじゃないか。いまなら自分を変えるのに言い訳が要らない」と読者の背中を押してくる。
乗せられやすい読者は、「新しいことか…。」と、物語の先にある未来に、ちょっとワクワクしながら本を閉じることになる。