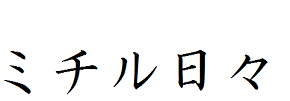『君たちに明日はない』という、なんか悲壮なタイトルで、物語は、リストラ代行会社の「仕事ぶり」を描く。
『君たちに明日はない』という、なんか悲壮なタイトルで、物語は、リストラ代行会社の「仕事ぶり」を描く。
が、遠くブラジルやコロンビアをその舞台に物語を描こうとも、必ず今の日本への辛らつな批判…と最後に希望を描く垣根ワールドは、この物語でも健在。
その切り込み方が、さらに深く面白く、つい最近はTVドラマにもなるほどの人気ぶり。
で、とうとう『張り込み姫』 (新潮社)は、シリーズ3作目となった。
2005年発行のシリーズ1と比べると、リストラされる人々の感覚がずいぶん違うなぁ…というのが、まずは素朴な感想。
主人公のリストラ代行会社面接官の活躍により、ほとんどの人が会社を去って行くのは同じだが、シリーズ1では、登場人物(=リストラされる人々)の”会社へのいわれなき期待”とか”しがみつきぶり”がリアルで悲惨だった。
一方、シリーズ3で描かれたリストラ物語は4つあるが、その登場人物は、揃いも揃って会社への期待は希薄だ。
たぶんゼロに等しいだろう。
登場人物は、会社にしがみつくこととか収入が途絶えてたのちの生活よりも、自分の好きな仕事をいかに続けてゆくかで悩む。
そして、ここではもう好きな仕事はできないと、会社を去ることを決意する。
いい感じだ。
”このまま居れば=例えば会社に残れば、「君たちに明日はない」”…という、実はそうゆうシリーズを通してのテーマがよりリアルになった。
「仕事のありかた」に真摯に向かう余裕がなく、「明日のお金」のことばかり考えざるを得ない多くの日本の会社は、静かにしかし確実に働くヒトから見捨てられる。
会社の多くも、最初はたった一人が見つけた新しいシゴトのカタチからスタートしたことを忘れている。
そうして、深い溝に落ちたまま、以前居た場所…はるか上方にかすかに見える光の当たる場所のことばかりを考えているが、「好きな仕事をしたい」人は、その落ちた溝に横穴はないか?
いっそ自力で掘ってやろうか!
…と新しいことを考える。
その皮肉な展開は、物語の中だけではなく、必然的に現実にも静かに起こっている…ようにも思えてくる。
この作家は、いつも、時代の半歩だけ先を見て、本当になりそうな希望ある物語を描く。
↓文庫もでました。