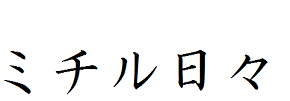梶井基次郎の『檸檬』は、初めて読んだ思春期には、文学的な面白さには、まったく気づかなかった
…と白状してしまおう。
最初は、実在する書店の美術書のコーナーのそこに、レモンを1個置いたというエピソードに憧れて紐解いた1冊でしかありません。
そのうち、2月17日の梶井基次郎の誕生日だと知ると、その日は、文庫版の『檸檬』を書棚から探し出し、気まぐれに紐解くのが、習慣のようもなった。
装丁が変わって復刻されたころ、私の持ってるそれもぼろぼろになって何度か買い替えもした。
そうして、少しずつ、その魅力に気づいてきた物語と作家なのかもしれません。
薄い文庫本1冊にこめられた瑞々しい世界
梶井基次郎の作品は、たった20篇あまりの小品のみで、この『檸檬』と表題された1冊を持っていれば、ほぼそこにすべてが収まってしまいます。
その本の薄さに、あまりにも短かった執筆の時期を悲しく思いつつも、やはり読み始めれば物語世界は非常に深く広く…そして美しい。
心情を切々と吐露する作風が多く、実際、いつの復刻版だったろうか、
文庫本裏表紙には「特異な感覚と内面凝視で青春の不安、焦燥を浄化する作品…」と描かれていたころもあり、確かにそうなのですが、しかし物語に重々しさのようなものはなく、瑞々しさのほうが勝っていると読むたびに思います。
そう感じるのは、物語に描かれた「色」の鮮やかさのせいでしょうか。
カンナ、ひまわり、駄菓子に花火、おはじき、電燈…そして檸檬
『檸檬』は、「えたいの知れない不吉な塊」に心を圧さえつけられながら、京都の街を彷徨う話なのですが、街をうろうろしながら主人公の目に映るものは、カンナやひまわりだったり、駄菓子やの花火や色硝子のおはじき。
読者は、いちいちその色合いを思い描きながら、自分の心も京都の路地へと入り込んでいきます。
檸檬を買った八百屋の描写にしても「店頭に点けられた幾つもの電燈が驟雨のように浴びせかける絢爛」などと表現され、だからこそ、その八百屋が非常に特別なものに思えてくる。
そして、最後の最後に、美術書を積み上げてその上に黄色いレモンを一個置く有名なシーン。
何か、ひとりの画家が、一枚の絵を仕上げたその瞬間を垣間見るような、あるいは美しい映像を見ているような、そんな気分にいつしか、しっかりと浸っています。
色彩の魅力は、その後の短編にもつづき…
文庫では、次作は「城のある町にて」が収録されていますが、それももちろんやはり色が密かにパワーを持っている。
冒頭から「I湾(伊勢湾)の濃い藍が、それの彼方に広がっている。裾のぼやけた、そして全体もあまりかっきりしない入道雲が水平線の上に静かに蟠っている」などと始められ、藍と白の組み合わせの美しさにとりこにされます。こうなれば、もう、物語の世界に入り込んだも同然。
どんどんどんどん深く入り込み堪能することになります。
冒頭からといえば、やはり有名な「桜の木の下には」の桜の色。
桜の下には死体が埋まっていると、冷静に読めばかなりシリアスな物語世界なのですが、まず、満開の桜であたりが薄ピンクに染められた様子を思い描き、その美しさにうっとりするところから始まる読者は多いのではないでしょうか。
少なくとも私はそうです。
作家の意図するところかどうかはわかりませんが、ここまで、この一冊の文庫本の世界を大切に思って来られたのは、物語に描かれた「色彩」のせいが大きいかったと思うのです。
そして、年を重ねて、梶井基次郎が31歳で逝ったのより、もっとずっと年上になって、やや「死」を意識し始めた年齢の今。やっと少し、物語の違う面が理解できるようになったかもしれません。
そして「丸善京都河原町店」
さて、美術書の棚を乱し、それを重ねた上に果物の檸檬が置かれた本屋は、かつて実在した「丸善京都河原町店」。
この書店は2005年10月10日に閉店しましたが、そのときを語るエピソードがあります。
「売り場の本の上にレモンを置いて立ち去る客が相次いでいる」と新聞やWEBのニュースにも取り上げられましたが、閉店が決まったと聞いて、ファン達がここに出かけては檸檬をこっそり置いていきました。
近くに住んでいたなら私もやりたいと記事を読んで即座に思ったニュースです。
書店員さんたちも、檸檬が宝探しのようで嬉しかったのでしょう。
書棚から見つけられた檸檬を籠に入れて『檸檬』の文庫本コーナーに飾っていたのだそうです。
京都河原町の丸善は、京都に旅した際は必ず立ち寄る好きな書店でした。
店の構造上か、なんとなく自分と本だけの世界に浸れるようなコーナーが多かったのがその理由のひとつ。
旅先の本屋というのは、実は落ち着かない部分もあるものですが、あそこは最初からしっくりくる不思議な場所でもありました。
逆に、それは書店員さんたちからは死角になる部分が多い店ということなのでしょうか、檸檬をこっそり置くにもさぞかしやりやすかっただろうと推測されます。
万城目学の文学的トリビュート
そのあたりの話は、万城目学の「ホルモー六景」の第三景「もっちゃん」にも描かれています。
もっちゃんは、梶井基次郎をモデルに描かれたキャラクターで、彼の青春時代について一般に語られるとおりのことをモチーフとして描かれた、しみじみとした物語。
そして、「もっちゃん」のエンディングが素敵です。
時代は、さかのぼり現代のシーンとして、丸善京都河原町店が閉店になる話が語られる。
「みんなが梶井基次郎の本を買い求めに来て、閉店直前の1週間で何と千冊も文庫が売れたそうだよ」
「ほほう、そいつはすごいな」
「最終日、営業時間を終えて、店の人が閉店の整理を始めると、フロアのあちこちから、お客さんがこっそり置いたレモンが見つかったんだってさ。」
これを読むと、なんだかちょっと嬉しくなり、だから実は、我が書棚には『檸檬』の隣には、『ホルモー六景』。
一瞬、異色の組み合わせの2冊を、そんな理由で並べているのです。