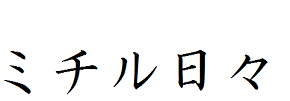澤田瞳子作『与楽の飯 東大寺造仏所炊屋私記』を読了。
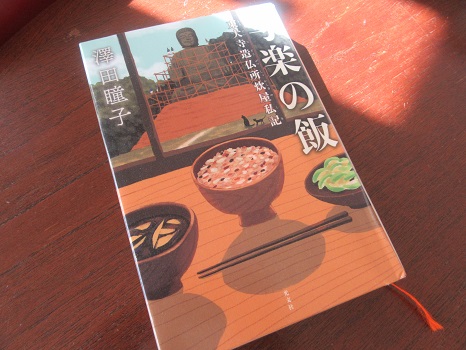
奈良時代の庶民の…というか、奈良東大寺・毘盧遮那仏の造営のために徴発された仕丁たちの日々の飯に、いきなり胃袋つかまれました。
仕丁は、地方から労役のため、中央(この物語の当時は、奈良)に招集された者たちの呼び名。
地方の若者たちの中から選ばれ、3年程度の労役についたのだとか。
物語の登場人物は、廬舎那仏造営のための肉体労働者であって、つまり、彼らが日々振る舞われている(といっても、一食につき米4合を払う、宿舎の賄いのようなものだけど)食事に、とことん惹かれたのである。
本書は、国家的大事業としてスタートした東大寺の大仏さま=廬舎那仏を造営した人々の話。
為政者の側からではなく、実際にその手でもって土を捏ね、危険な大仏鋳造にかかわったひとびとの目線から描いた話が珍しく、遠すぎる時代の話のせいで、なかなか読み進むのが困難になりがちだけど、最初から妙に引き込まれて読み進む。
やっぱ、メインのシーンが、炊屋(食堂)というのがいいのだと思う。
そこで饗されるメニューが、懇切丁寧に描かれていて、読者は、物語に寄り添いやすい。
さまざまに起こる事件も、登場人物をめぐる過去の謎解きも、みんなこの炊屋を通じて描かれる、連作短編集というのも読みやすい要因。
だから、、宮麻呂(みやまろ=炊屋の炊男(かしきおとこ)つまり料理人)、真楯(またて)、小刀良(ことら)、鮠人(はやと)(=彼らは同じ日に配属された)、猪養(いのかい=仕丁頭、仕丁をまとる世話役的存在。)、その他、舎薩(しゃさつ) 馬馗(うまくび)、乙虫(おとむし)、牟須女(むすめ)…と、登場人物の名前も役職名も、なんだかもう耳慣れないけど、物語には早々に入り込んでしまった。
…って、これ私にとっては珍しいんですよね。
そうそう、奈良も「寧楽」。
まったくもって、「食べ物」のチカラってすごいです。
わたしだけかな?
せっかくなので、宮麻呂(みやまろ)が作って饗した献立の数々をまとめてみる次第。
飯は、おおむね赤米や稗混じりの雑飯(雑穀米)。
で、あとは一汁一菜ながら、現代の食に優るとも劣らなさそうな印象なんですよねぇ…これが。
・干した茸と青菜だけの塩汁、茸の風味が濃厚と、素焼きの小皿にのった瓜の塩漬け
・干魚の焼き物と皮骨入りの汁
・いのしし汁と干し菜の塩漬け
ちなみに、いのしし汁は、作り方まで描かれていて、こんな風。
⇒肉を炒めたあとに、鍋にざばっと水を注ぎひと煮立ち、野びる(ねぎの一種)と戻した干しかぶらをいれたもの。最後に刻んだ青菜と蜀椒(なるはじまみ=山椒の実)を加える。
・薺嵩(うはぎ)飯(=ヨメナの菜飯)+鶏の醤焼き
・焼鮒に蕨の塩漬け
・茄子の汁に焼鮒、早生の李子←この日はデザート付き!
・干し葉を刻み込んだ菜飯に、鶏の油煮(揚げ物)、薑(はじかみ=生姜)入りの茸汁
…うーん。またもおなかがすきました。
まだまだあるけどこの辺で、興味ある方は、本書で食のシーンを拾い読みしてください。それだけでも楽しいです。
エンディングで語られる宗教観に、深く心を打たれました。
そうして、食べ物に惹かれて読み進み。
仕丁たちをめぐる、ややハードな日常によりそいつつ、主人公のひとり、炊男(かしきおとこ)宮麻呂に隠された暗い過去も垣間見つつ。
しかし、その宮麻呂が吐露した宗教観…というか信仰のカタチに、ふかく同意するのである。
曰く「あの巨仏は、わしらがくたばった後も、幾百、いや幾千年もの長きにわたってこの地に残り、貴賤の者より礼拝を受けよう。おぬしらは上つ方々のために大仏をつくっておるのではない。後の世に生きるものたちのため、自らの身を削って仏に変えておるのじゃ」
廬舎那仏は、完成したからそこに仏が宿るのではなく、その日から長い年月をかけた、何千何万という人々の祈りのエネルギーの集積によって仏になる…ってことか。
そう解釈しつつ、ちょっとわが身が打ち震えたりもした。
最後に、太陽の化身とされた廬舎那仏を完成させる莫大な量の「金」のコト。
このことに併せ触れられる陸奥の話に興味津々。
本作では、深く語られることはなく、ただ、差別される悲しい存在としてしか描かれていないけれど、今度は、続編的に、陸奥の民の話を書いてほしい。
東北育ちの私としては、そんな風にも読める一冊。
そして、この一冊を読んで後の奈良の大仏さまは、以前の大仏様とは、もう全然別の存在になっているという事も、重要な読後感。
読了した今、もしも、奈良に出向いて、大仏を見上げることがあるとしたら、きっと涙が湧き出てくると思う。
↓買って損のない1冊だわと思う。