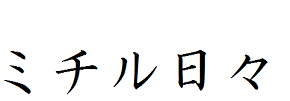2月13日、佐藤さとるさん誕生日記念にて、
コロボックル物語シリーズ1「誰も知らない小さな国」を再読いたしました。
もう何度目の再読か不明。
それでも、ちゃんとドキドキワクワクしつつ読み進め。
ときどき涙。
ってことで…。
「コロボックル物語」の第一作目をココにレビュー
佐藤さとるさんによる「コロボックルの物語」は、ある夏休みの1日、少年が「虫のような」小さな人と出会った出来事で始まります。
村のおばあさんから聞いた、鬼門山に暮らす小法師さまの伝説。
少年は、1度その小法師さまにぜひ会ってみたいものだと思い、そして実際に出遭ってしまいます。
川を流れてゆく小さな赤い運動靴に乗った小指ほどしかない人たちが、少年に向かって手を振っている。
少年が、夏休みの最後の日に見た、夢とも現実とも判断がつかない光景でした。
やがて、大きな戦争がはじまり、平和な日常はその戦争の渦の中に巻き込まれてゆきます。
そして、終戦、渦にもまれて逃げ惑ってようよう生きぬいてぽっかり空いた何も無い日々。
ふと、あの鬼門山の小さなひとびとのことを思い出します。
少年は、ひといちばい背の高い青年になっていました。
青年と小さなひとたちの再会のシーンは感動的です。
この物語は、1959年、高度経済成長の入口で、ひっそりと生まれたけれど、すぐに大きな賞をたくさん受賞し人気の本になりました。
当時の小学校の図書室にも近所の図書館にも必ず置いてある本だったのではないかと思います。
そして、何回も借り出すリピーターが多く、いつも貸し出し中の本でもありました。
やっと借り出したその本を好きに開くと、まずは、その再会シーンのぺージが現れる。
そのページから、綴じがほつれかかっていたような記憶すらあります。
物語好きの子どもたちよって、そのページだけ何回何回もも読み返されたのは公然の事実。
結局、つぎに借りた読者も、開き癖が付いたそのシーンを何度も何度も読み返し、涙するはめになりました。
小さな人たち=コロボックルから、やがて青年は「せいたかさん」と呼ばれます。
そして、鬼門山はずっと昔からコロボックルの住む場所だったと教えられます。
コロボックルたちは、せいたかさんに味方になってもらえるように望み、彼も山の麓に住んで彼らの国を守ってゆく決意をします。
高度成長時代の功罪を密かに忍ばせた物語でもあった
高度経済成長は、日本人の生活を豊かにした一方で、科学万能と経済発展を錦の御旗に、ひっそり静かに存在していたものを暴いてゆく時代でもありました。
実際、このお話のクライマックスも、車専用の道路建設のために鬼門山をつぶす計画が持ち上がり、それをせいたかさんとコロボックルたちが協力して阻止してゆくという話で展開してゆきます。
鬼門山に住む小さなひとたちの存在は、そうゆう時代の雰囲気によって暴かれるものの象徴としても描かれている。
大人になって読み返してそこに気づき、リアルな時代背景とファンタジーの接点が面白くも悲しく感じられます。
神話やアイヌ伝説、そして、目に見えないけど存在するものへの興味
また、物語には、小さな人たちを「せいたかさん」はコロボックルだと信じ、小さな人たちは、「われわれのご先祖は、スクナヒコさまだ」というやりとりがあります。そこで、作者は、物語の中で、アイヌの伝説や日本の神話にも詳しく触れて、実は、小学生の頃には、そこが、ちょっと難しかった。
しかし、面白い物語のチカラとはすごいものです。
結局、読者の好奇心の根っこを新しい世界へどんどんのばす役割までも果たしてゆきます。
少なくとも、私の、神話やアイヌの伝説への興味は「コロボックル物語」が入口だった。
そしてそんな読者が多かったことも、大人になって同じ読書体験を持つ友人にであって確信したのです。
科学的に証明できるものが価値あるものと、世の中の評価基準が極端にバランスを欠いてゆく時代。そこで育った高度経済成長時代のこどもたちが、それでも科学で説明できないものに惹かれる大人になった。
迷信とか、神さま仏さまとか。
そこに、妖怪とか、怪獣とかまで含めれば、ほらね、否定の余地はありません。
それは、こんなファンタジーをわくわくしながら読んで、心を耕してきたからなのだとつくづく思うのです。
これが、佐藤さとるさんの「コロボックル物語」の入口の話。
そこから、シリーズは続き、スピンアウト物語なども。
この世界にありそうでなさそうで、やっぱりあってほしい物語をこの作家は縦横無尽に紡ぎだしてゆくのです。