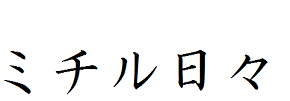今年の「蕗の薹」の頃は、東京なら3月上旬(中旬は育ちすぎだったんで)、福島あたりはお彼岸のころでした。
そこから早ふた月が過ぎ、蕗の旬もそのぐらいの時間差でやってきます。
東北の街で過ごしたゴールデンウィークには、蕗の薹は花咲いて立ち枯れて…。
その界隈には、若き蕗の葉の群生。
あら、ステキ! この柄を参考に何かできないかしら、と毎度恒例無駄な思考も始まって…。
編み込みのサマーセーター?
→うーん、となると、全然ステキじゃないかも。
こんなテキスタイルの布はどお?
→布地じたいはステキそうだけれど、それで何か作ったとたんにかっこ悪くなるかもね。
うーん、うーん。
などと、美的センス皆無なのか、なんのアイデアも生み出せない(しくしく・涙)。
そうこうするうち、東京へ帰ると、スーパーや八百屋のいちばんいいところに蕗の束。
お値段も、たぶん、今ごろが底値かも。
…という具合です。
そしたら、葉付きの蕗を買って来て、下ごしらえの苦労まで買ってしまうのは、毎度のコト。
それは、山野に自生するのを採って食べるみたいなことに、どこかで憧れているからかもしれません。
さて、蕗は葉と茎にわけ、まずは葉っぱを熱湯でさっと茹で、しばらく水につけておく。
のちに、細く切って油で炒め、砂糖、酒、醤油、たかのつめ少々。
蕗の佃煮である。
蕗の旬は初夏だというのに、ほろ苦さがあって、まだ春を少し受け継いでいるかのようです。
次は茎。
塩をぱらりと振りかけて、まな板で板擦りして、産毛を落とす。
ここで、思いがけずに、鮮やかな黄緑色になって、毎シーズンの付き合いだというのにいつも小さく驚きます。
熱湯でさっと茹でて水に晒せば、さらに瑞々しい緑色になって、目にもまぶしい。
うっとりする間もなく、これからが、下ごしらえの本番。
一本一本、無心になって、爪で丁寧に皮を剥いてゆきます。
…いやいや無心というのはちょっと嘘です。
手は蕗のシゴト、ココロは蕗の話をひとめぐり。
まずは、各国の大名を相手に不名誉事件の渦中に落ちたお殿様の話。
秋田には、この茎が2メートルにも育つ秋田蕗というのが昔から名物としてあり、江戸時代には、秋田藩のお殿様が秋田の蕗は傘になるほど大きいと自慢してしまう。
しかし、他の大名に誰ひとりとして信じるもの無し。
蕗の話ごときで武士の不名誉に発展してさあ大変です。
そこで、領民たちは、お殿様のためにとひとはだ脱いで、傘にもあまる、一本の大きな蕗を江戸に運こび、藩主の名誉は回復されたのだそうです。
しかし、ココで私のココロを占めるのは、領民たちの忠誠心ではなくて、茎が2メートルもあったら、この下ごしらえもさぞかし大変だろうな…と(笑)。
秋田のヒトは、蕗の下ごしらえを、実際どんな風にしてるのかしら?
次には、蕗の傘さすコロボックルがひょいと顔を出す。
コロボックルは、アイヌ語で、「蕗の葉の下の人」という意味。
日本の神話にも登場する少彦名命をカミサマとする小さな人たちが、蕗の野原を駆け巡る冒険談など思い描いたりもする。
(何それ?という方はどうぞこの本をお読みください。面白いよ!)
しかし、どんなに剥いても、まだまだたくさんの蕗の茎。
そして、わが手元を見れば、この宝石のように鮮やかな緑のどこにこんな闇色が潜んでいるのかと思うほど爪は見事に黒く染まっていました。
蕗は、古くから日本の野山に自生していた野草。そして日本古来の野菜です
蕗は、ずーっと前から日本人とともにあり、栽培が始まったのは、記録に残っている限りでは、平安時代だとされています。
当時の漢和辞典『新選字鏡』や薬草辞典『本草和名』にもすでに蕗は布々岐(ふぶき)という名で登場し、食用されていたと書かれているそうで、つまり、数少ない日本古来の野菜の一つ。
ほーっ。
しかし、そこで思うことは、ただひとつ。
蕗は、すいぶん昔から、下ごしらえするヒトの爪を灰汁で黒く染めていたわけだねぇ…と。
蕗の皮をつつつーっとひと剥き、平安時代の初夏と今が繋がりました。
ああ、めんどくさい、手が疲れたと思っても、やっぱり1年に1度のこの苦労が楽しいのは、こんなコトが理由なのかもしれません。